概要
1分で読めるまとめ版
〇使役文=「人が人に何かをさせる」文
・能動文「エマがピーマンを食べる」
・使役文「母親がエマにピーマンを食べさせる」
〇主語と助詞の変化
・他動詞の使役文:主語=使役主(母親)、二格=動作主(エマ)
・自動詞の使役文:主語=使役主、ヲ格=動作主
〇使役文の3つの用法
1.許可:
したい人に「いいよ」とさせる(例:子どもに食べさせる=食べたい子に許可)
2.強制:
したくない人に「ダメ、しなさい」とさせる(例:子どもに食べさせる=食べたくない子に強制)
3.他動詞的表現:
動作主が自分でできない時に、使役主が対象に直接働きかけて実現させる(例:母親が子どもにご飯を食べさせる=実際には母親がスプーンで口に運ぶ)
〇無意志動詞の使役もある
・「花を咲かせる」「腐らせる」などは「他動詞的な使役」に含まれる。
●ポイント:
「誰の意志で動作が行われるか」 を押さえる。
・許可/強制 → 動作主の意志あり
・他動詞的表現 → 動作主の意志なし(使役主が直接介入)
1分で読める整理表
【使役文の基本構造】
| 種類 | 主語ガ格(使役主) | 二格 / ヲ格(動作主) | 使役動詞 |
|---|---|---|---|
| 他動詞の使役 | 母親が(使役主) | エマに(動作主) | 食べさせる |
| 自動詞の使役 | 母親が(使役主) | エマを(動作主) | 走らせる |
【能動文⇒使役文の主語と助詞の変化】
| 種類 | 能動文 | 使役文 | 主語 | 動作主 | 動詞の変化 | 助詞の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他動詞 | エマがピーマンを食べる | 母親がエマにピーマンを食べさせる | 使役主=母親 | 動作主=エマ | 食べる→食べさせる | 「が」→「に」/「を」変化なし |
| 自動詞 | エマが走る | 母親がエマを走らせる | 使役主=母親 | 動作主=エマ | 走る→走らせる | 「が」→「を」 |
【意味用法の比較表】
| 用法 | 説明 | 動作主の意志 | 例文 |
|---|---|---|---|
| 許可 | やりたい相手に許可する | あり | 母親が子どもにご飯を食べさせる(子ども→食べたい) |
| 強制 | やりたくない相手に無理にさせる | あり | 母親が子どもにご飯を食べさせる(子ども→食べたくない) |
| 他動詞的表現の使役 | 意志のない対象に働きかけて行為を実現 | なし | 母親が子どもにご飯を食べさせる(口に運ぶ) |
| 無意志対象の使役 | 自然現象などを変化させる | なし | 太陽が花を咲かせる |
使役文の基本構造とつくり方
使役文の基本構造
| 種類 | 主語ガ格(使役主) | 二格 / ヲ格(動作主) | 使役動詞 |
|---|---|---|---|
| 他動詞の使役 | 母親が(使役主) | エマに(動作主) | 食べさせる |
| 自動詞の使役 | 母親が(使役主) | エマを(動作主) | 走らせる |
使役形の活用
使役形の動詞の活用についてはこちらの記事をご参照ください。
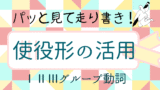
使役動詞と格の変化(他動詞・自動詞)

はじめの文を使役文にすると、動詞は使役動詞に変わります。
使役文になると、新たな人物が加わり主語が変わります。
✓動詞➡使役動詞
他動詞の使役文
エマがピーマンを食べます。
【使役文】
母親がエマにピーマンを食べさせます。


使役文では、
主語は指示などをするだけ(使役主=母親)の人で、
実際に食べる人はニ格にあたる人(動作主=エマ)です。
※はじめの文…能動文
※使役主…使役文においてある行為をさせる人。
※動作主…その行為をする人。
自動詞の使役文
自動詞の使役文の場合は「二格」ではなく「ヲ格」にあたる人が動作主です。
エマが走ります。
【使役文】
母親がエマを走らせます。
【他動詞・自動詞の見分け方についてはこちら↓↓】
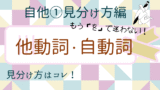
使役文の3つの意味用法|許可・強制・他動詞的表現

使役表現の意味用法の分類には諸説あるようですが、それは「使役」という言葉の意味をどう捉えるかによって変わってきます。
本記事では、「使役」の基本的な意味を「人が人に何かしらの行為をさせること」といった人間関係を軸にしたものであるとします。
それはすなわち「使役主が動作主に何か行為をさせること」であり、
また「動作主が自らの意志をもってその行為を行う」ことが動作の実現であるとし、使役の用法を考えていきたいと思います。
✓「人が人に何かをさせる」=人間関係が軸
✓ 動作主の意志を伴う
ここでは、大まかに使役の代表的な用法二つとそこに分類しづらいパターンの一つを
「母親が子どもにご飯を食べさせる」
の例文に沿ってご紹介します。
①許可の使役
使役表現の意味用法の代表格の一つが「許可」です。

これは、「食べたい子ども」に対して「いいよ」と母親が許可を与える表現です。
動作主(子ども)は自分の意志で食べます。
②強制の使役
使役表現の意味用法の代表格のもう一つが「強制」です。

こちらは、「食べたくない子ども」に対して母親が「ダメ。食べなさい」と積極的にその行為を動作主に強いる表現です。
そして、動作主(子ども)は自分の意志で食べることになります。
③他動詞的表現の使役
上記の①「許可」と②「強制」が使役表現の用法説明としては割と代表的ですが、「子どもにご飯を食べさせる」にはこういったパターンも日常ではよく見られます。

このパターンが①許可②強制と大きく違うのは、ここで言う「使役」の意味が強く含まれていないところです。
まず、③の動作主(子ども)はしっかりとした意志を持ってご飯を食べることができません。
つまり、この絵の状況は、動作主(子ども)が使役主(母親)の指示などによって「自分でご飯を口に運んで食べる」わけではなく、
代わりに、母親が動作の対象である「ご飯」に直接働きかけることによって「子どもがご飯を食べる」という動作が実現しています。

これは使役表現というよりも、人の対象(物)への働きかけ表す他動詞的表現に近いと言えます。

能動文ぽい使役みたいな、使役感のうっすーい使役みたいな。
まるで「母親」が影武者みたいになっているね。

自他④「寝かせる」「寝させる」の違いの記事の中にもあった「その動作を行う人の意志あるかどうか」という点がこの分類にも表れているね。
無意志動詞の使役|「花を咲かせる」

これは自他③記事であった「他動詞の代わり」ですね!

「咲かせる」「腐らせる」といった無意志動詞が使われる場合の使役文も、他動詞的表現に含みます。

確かに。
例えば、「走りなさい」と指示されて「はい、走りまーす」は言えるけど、「咲きなさい」と指示されて「はい、咲きまーす」とはならないもんね。
でも、何らかの働きかけによって「花を咲かせる→花が咲く」ことはできる。
「基本的な使役」と「他動詞の代わりとしての使役形」の違い
| 用法 | 主な意味 | 働きかける人 | される人・もの | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ①使役(基本的意味) | 強制・許可など | 明確に存在(人など) | 明確に存在(人など) | 強い人間関係性や意志を伴う |
| ②他動詞の代わりとしての使役(代用表現) | 変化の原因 | 明確、あるいは抽象的(自然現象など)に存在 | もの・事象が多い | (自他ペアになる)他動詞がない時に、その意味を補う目的で表現 |
表で比較|使役文とその意味の違い
| 用法 | 説明 | 動作主の意志 | 例文 |
|---|---|---|---|
| 許可 | やりたい相手に許可する | あり | 母親が子どもにご飯を食べさせる(子ども→食べたい) |
| 強制 | やりたくない相手に無理にさせる | あり | 母親が子どもにご飯を食べさせる(子ども→食べたくない) |
| 他動詞的表現の使役 | 意志のない対象に働きかけて行為を実現 | なし | 母親が子どもにご飯を食べさせる(口に運ぶ) |
| 無意志対象の使役 | 自然現象などを変化させる | なし | 太陽が花を咲かせる |
【他動詞についてはこちら↓↓】
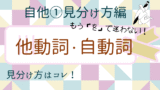
【参考文献はこちら】
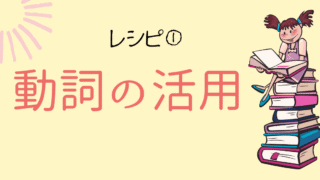
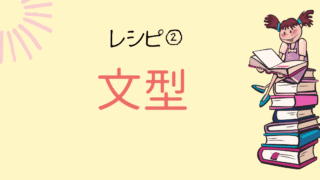
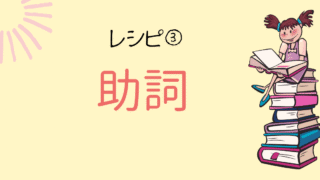
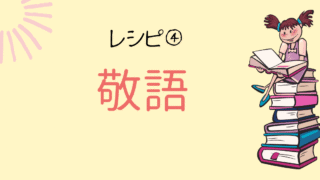
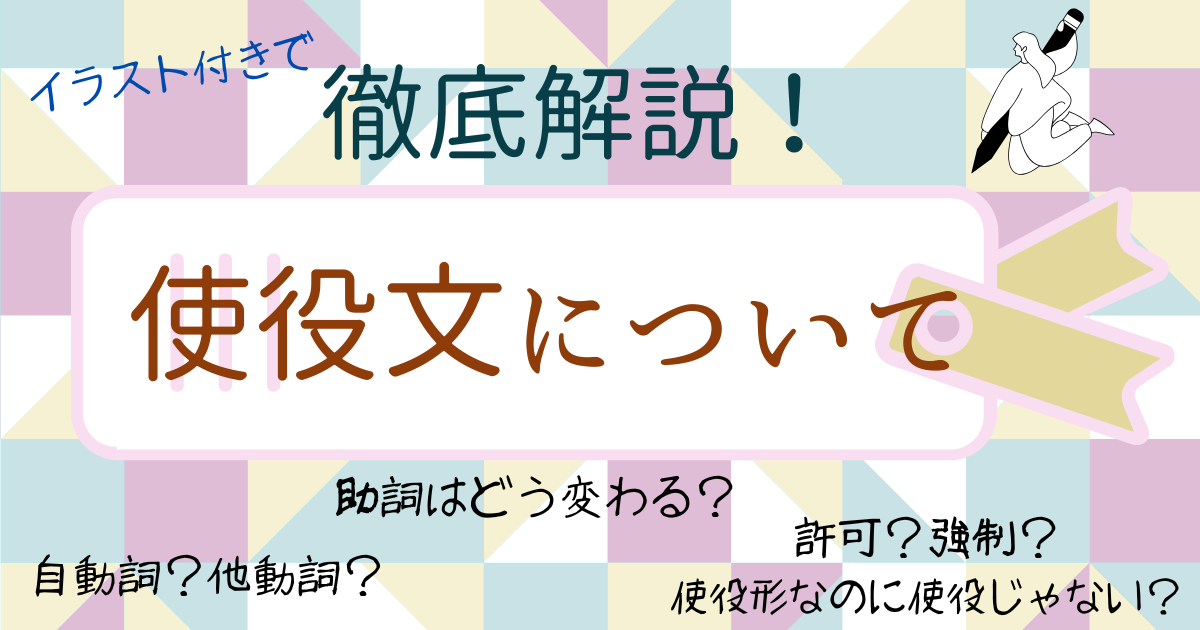
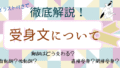
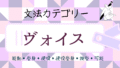
コメント